3年ぶりの「大感謝祭」に立つ男
秋晴れに恵まれた2022(令和4)年11月12日、横浜市にある大型展示場「パシフィコ横浜」に、全国から100以上の自治体が集結した。それぞれの「ふるさと納税」をPRするためだ。
2日間の日程で開催されたのは「ふるさとチョイス大感謝祭2022」。寄附者であるユーザーをリアル会場に招待して実施したのは2019(令和元)年以来、3年ぶりとあって、待ちわびた大勢のファンで熱気に包まれていた。
その一角、都城市のブースを覗くと、ひときわ人口密度が高い。所狭しと5〜6人が動きまわり、来場者に試食してもらうローストビーフを準備していた。その数量は2日間で計1400食。牛肉の重さにして50〜60kgもある。

試食用に計1400食用意されたローストビーフ
試食の配布時間が訪れると、色黒の男性が一人ひとりにローストビーフの小皿を手渡し始めた。聞けば3年前も同じイベントでローストビーフを配ったという。
ちなみに、彼は都城市役所の職員ではない。都城のふるさと納税に返礼品を提供する事業者の一つ、ばあちゃん本舗(宮崎県都城市)の小園秀和社長だ。

ローストビーフを配る、ばあちゃん本舗の小園秀和社長
ほかにも応援に来ていた民間事業者が3人いた。休憩していたメンバーも加えると民間から4人、都城市役所から来た4人と合わせて8人という大所帯。多くの自治体が数名の職員のみ、あるいは民間事業者がいても1〜2人というなか、都城のブースはかなり手厚い布陣に見えた。
民間からの応援部隊はいずれも、「都城市ふるさと納税振興協議会」の加盟社。この協議会が、今回のストーリーの主役である。
「全国でも例がない、うちだけの取り組み」
これまで、表面では見えない「ふるさと納税における都城の真の強さ」、その裏側にある「行政の変革」を追ってきた。
「ふるさと納税日本一」だけでは測れない実力 都城市8年連続トップ10の偉業
都城市ふるさと納税大躍進のなぜ[前編] 起点となった「対外的PR戦略」
しかし、行政の変革は、都城市のふるさと納税が大躍進を遂げた大きなきっかけではあるが、「8年連続トップ10入り」という偉業の根拠としては弱い。
2015(平成27)年度に「ふるさと納税日本一」となった都城市が、その後も勢いを落とさず強さを持続できた背景には、行政側の“覚醒”に呼応するように意識変革をした民間事業者の存在がある。その中心となったのが、都城市ふるさと納税振興協議会(以降、振興協議会)だ。
同協議会は、都城市のふるさと納税に参画する民間事業者が加盟している任意団体。名称から、「市と結託して、市の税金で(あるいは補助金で)甘い蜜を吸っている組織だろう」と訝しむ人もいるかもしれない。
しかし、この民間事業者団体に公金は1円たりとも入っていない。
今や、加盟する事業者が137まで増えた振興協議会の予算は、2022年度で1億4410万円。その約7割が、都城市のふるさと納税をPRする広告宣伝やイベント、グッズ制作などに使われているが、すべて民間事業者が自らの売り上げから供出する「負担金」によって賄われている。“自腹”でふるさと納税の振興に努めているのだ。

出所:都城市ふるさと納税振興協議
「全国でも例がない、うちだけの取り組みで、官民一体の新しいかたち。今から始めようと思っても真似できないような取り組みをしている」――。都城市でふるさと納税を担当する「ふるさと産業推進局」の野見山修一 副課長はこう話す。
この振興協議会が果たしてきた役割や貢献は、意外と知られていない。都城市がふるさと納税のリニューアルを実施した翌年に時計の針を戻そう。
きっかけは居酒屋での何気ない一言
2015年8月の暑い日、都城市内のとある居酒屋。そこで、市役所職員や返礼品の納入事業者などが入り混じり、暑気払いの宴会が催されていた。
折しも、都城のふるさと納税はかつてないほどの急成長を見せ始めた時期。2014(平成26)年10月に「肉と焼酎」を基軸としたふるさと納税のリニューアルを実施して以降、都城市への寄附金額は前年度比約52 倍の約5億円と飛躍的に伸び、全国の自治体で9位に急浮上した。
リニューアル2年目の2015年度もその勢いは増し、結果として前年度比8.4倍の約42億円を集め、初めて日本一となった。暑気払いは、その年の夏のことだった。勢いを肌で感じていた参加者も興奮を隠せない。
「市役所も頑張って盛り上げてくれている。自分たちも、なにかお手伝いできんやろか。例えばみんなの売り上げの1%を集めてPRグッズを作るとか」
返礼品を提供する民間事業者の一人、都城市菖蒲原町で日向屋酒店を経営する平瀬修氏がそう口火を切ると、居合わせた何人かの事業者も「いいねぇ」と返した。

日向屋酒店を経営する平瀬修氏は「広報 都城」で紹介されたことも
宮崎牛と一部のブランド豚、そして、霧島酒造の黒霧島に赤霧島。それらに返礼品を限定した2014年10月から15年9月まで、返礼品を提供する事業者は20ほど。その誰もが「もっと民間の立場でふるさと納税を盛り上げていきたい」という思いを抱いていた。
一方で、実際に申し込みがあるかどうかわからない大量の在庫を抱えるリスクや、ふるさと納税の制度自体がいつまで続くかわからない先行きに不安も感じていた。
「でも、そんなに簡単にはいかないよね」。このときの話は、そこで終わった。
市役所が直面した「贅沢な悩み」
暑気払いから数カ月が過ぎた2016(平成28)年の年明けのこと。当時、都城市役所でふるさと納税を管轄していた総合政策課は、ある贅沢な悩みに直面していた。
その頃、ふるさと納税のポータルサイトは、ふるさとチョイスの一強時代。そのデータから、2015年1〜12月の暦年で、都城市への寄附額が全国1位になったことがわかった。よほどのことがない限り、総務省による2015年度(2015年4月〜2016年3月)の集計でも1位となるはずだ。
ふるさと納税のリニューアルの目的は、都城市の名前を全国に売る「対外的PR」。であれば、「日本一」も大々的にPRすべきだ。しかし、市役所としては予算が取りづらい。
すでに来年度予算は組まれている。予備費から追加予算として捻出するにしても、かなり煩雑な手続きを必要とするため、タイミング良く、広告などを打てない可能性が高い。そもそも、当時の自治体全般に、広告宣伝費というものを税金で賄うことが難しい空気があった。
どうしたものか。当時、総合政策課の副主幹としてふるさと納税を担当していた野見山副課長は、上司の吉永利広課長(現・副市長)に相談し、ある結論に至った。それが、暑気払いで出たアイデアの具現化である。
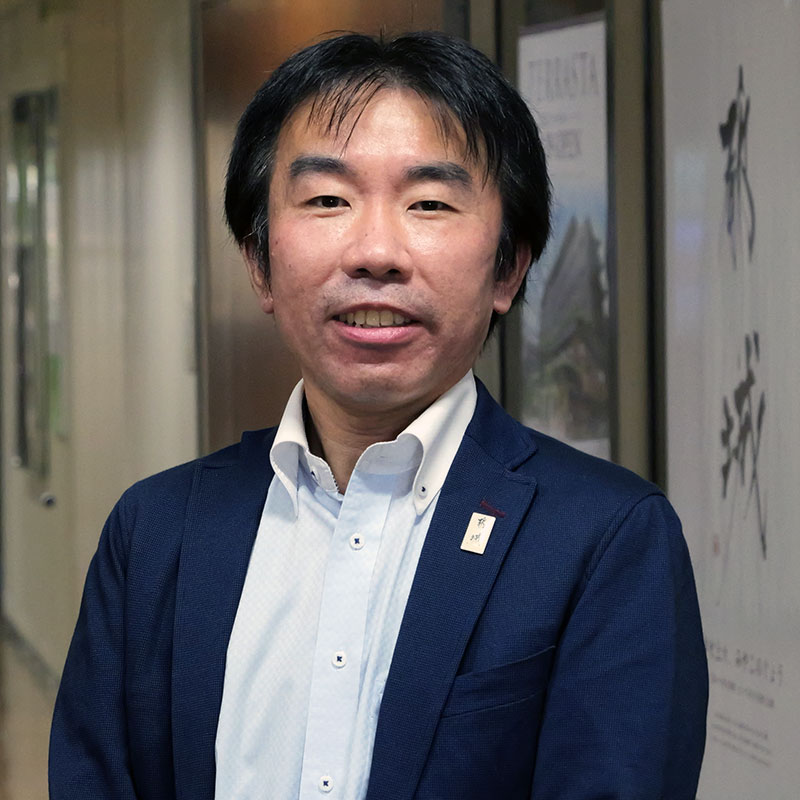
ふるさと産業推進局の野見山修一副課長
2016年1月下旬、総合政策課は返礼品を提供してくれていた21事業者すべてに声をかけ、2月に説明会を行った。
都城市役所秘書広報課前の会議室。全事業者が居並ぶ前で、総合政策課はこう提案をする。
せっかく盛り上がって伸びている都城のふるさと納税をもっと加速させて、皆さんの収益にも貢献したい。平瀬さんから「自分たちもお金を出しあって」とお話があった。税金ではなく、事業者が出し合った負担金の予算で広告などのPR活動を強化し、それが事業者の売上高に還流するような仕組みを皆さんで作っていただけないでしょうか――。
「職員の努力を見てきている」
当初、市役所が提示した「負担金」は、ふるさと納税関連の売上高の「5%」。つまり、返礼品を提供する事業者は、既存の各種税金に加え、新たに5%の税金を取られるようなものであり、通常であれば反発は必死だ。ところが、どうも様子が違ったのである。
冒頭で紹介した、ふるさとチョイス大感謝祭の手伝いに出ていた小園社長も説明会に出席した一人。市役所の面々ともこれが初対面だった。彼は当時をこう振り返る。
「当時のふるさと納税に参加する事業者はまだ少なかったですが、皆が同じ方向を向いているわけではなかった。ただ、自分としては、日本一になったはいいけれど、それだけクレームも増えるだろうし、ふるさと納税自体がいつまで続くかもわからないなかで、事業者が一枚岩になる必要性も感じていました」
「なにより、市役所の皆さんが、臨時職員さんも含めて、コールセンター業務みたいなことまでしてくれている。ときには、夜の12時1時まで、一生懸命、ふるさと納税のためにやってくれている。そういう姿を見ていたのが一番大きかった。そのおかげで僕らの売り上げも上がっているわけで、協力できることはしたいという気持ちのほうが強かったです」
「ただ、『5%』に関しては、うちの経理も『でかいな』と言ってましたけれど(笑)」
じつは小園社長、市役所の職員がいかに縁の下で努力をしているのか、周囲の事業者仲間に内々でことあるごとに話していたという。なぜ、返礼品を「肉と焼酎」に絞ったのかなど、市役所の「対外的PR戦略」とその先のビジョンなども、市役所に代わって仲間に説明していた。
そういった“地ならし”が奏功し、民間事業者で資金を出し合う協議会の設立に関して、異を唱える事業者は存在しなかった。
負担金の比率も、最終的には各事業者が返礼品収入の2%を拠出すれば、PRやイベント、事業者の研修など、想定していた施策を実行できることがわかり、満場一致で合意。こうして2016年3月29日、民間事業者団体が運営資金を拠出する、全国でも例がないふるさと納税振興のための組織が都城で立ち上がった。
(後編に続く)
自腹で集結、民間事業者の功績 [後編] 「振興協議会」でなければできないこと


